やや駆け足でたどってきたサウンド制作の変遷第2章ですが、しめくくりとして、サウンド専用ハードウェアがなくなり、ソフトウェア制御となった世代から、マルチプラットフォームに向けたサウンドシステムの取り組みについてお伺いしていきます。
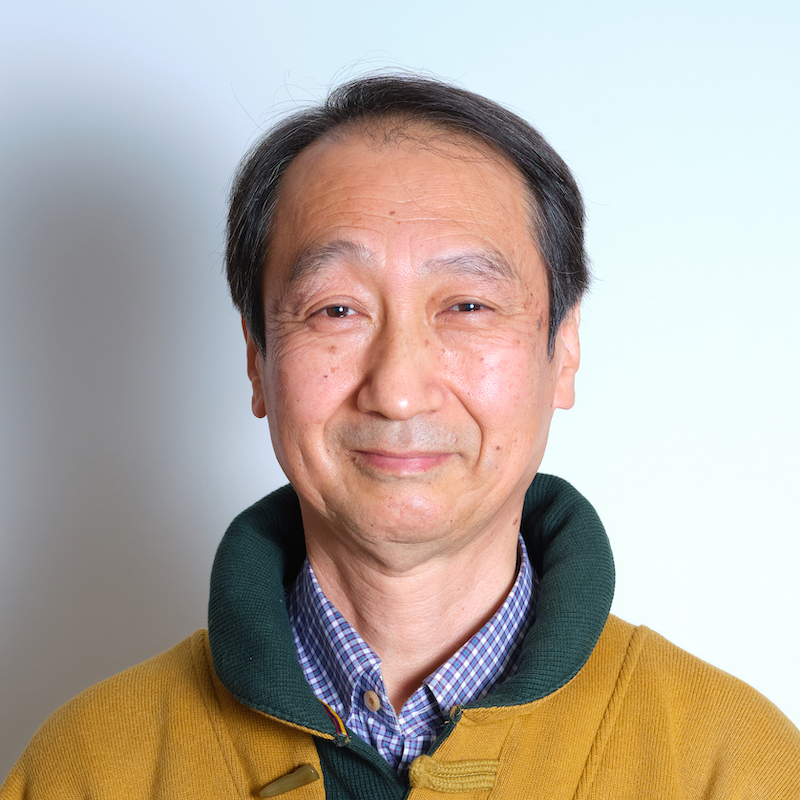
小川 徹
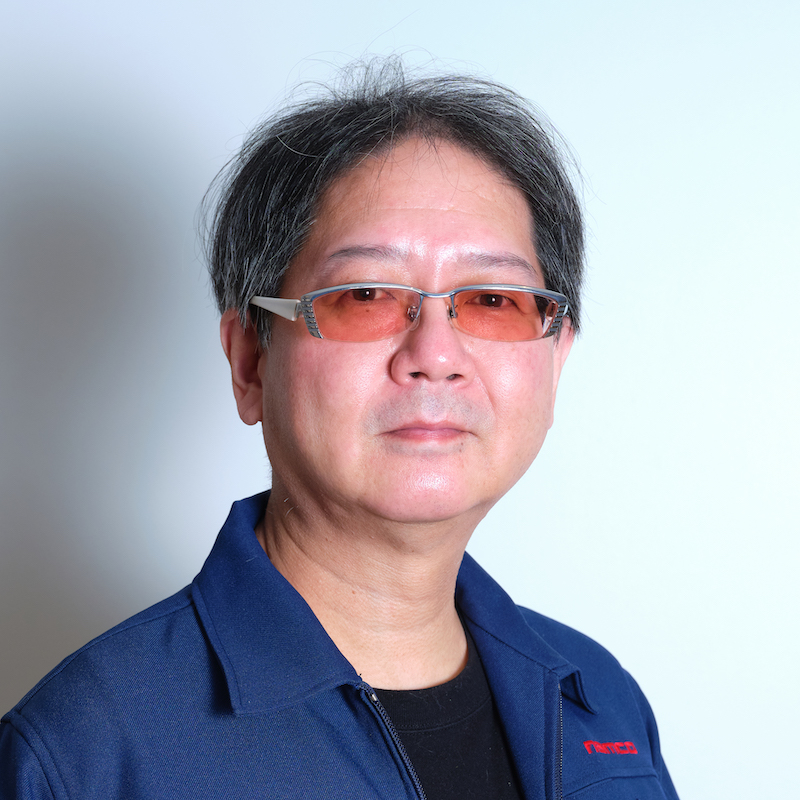
細江 慎治
1985年、ナムコ(当時)のテストプレイにアルバイトとして参加、同年グラフィックの手伝いを経て、秘密裏に『ドラゴンスピリット』にサウンドを載せて1987年正社員登用。花博(1990年:国際花と緑の博覧会)に出展した『ギャラクシアン3』、『リッジレーサー』、『スピードレーサー』等を担当。1996年退職後も「リッジレーサー」、「鉄拳」シリーズ等や他に参加。現在は作家としても活動中。
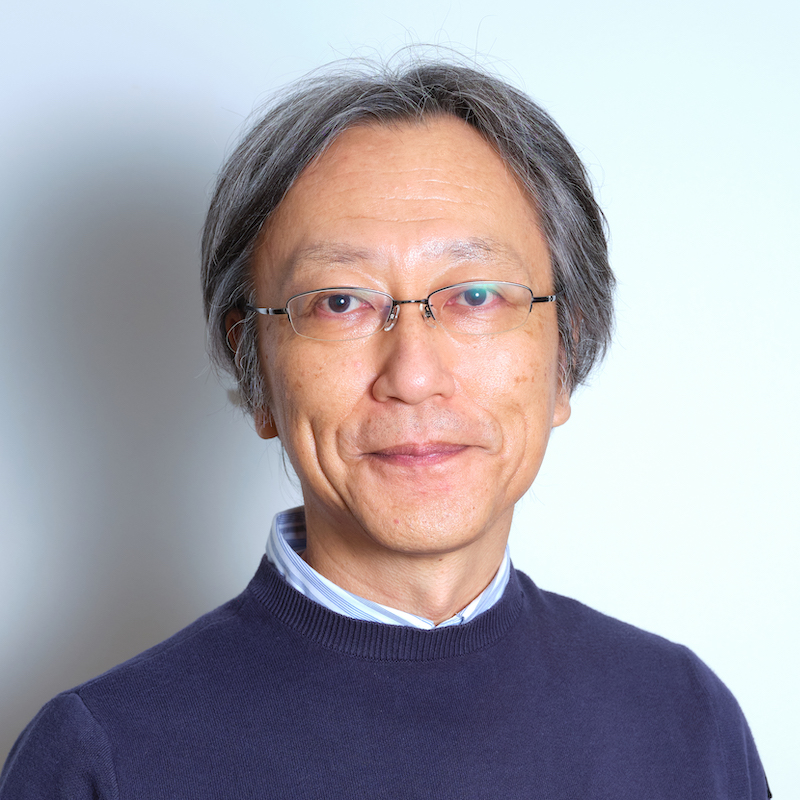
川田 宏行
1984年、ナムコ(当時)に入社。 開発企画課での『スターラスター』、『ワルキューレの冒険』開発を経てサウンド部門へ。『妖怪道中記』、『ワルキューレの伝説』、『ソルバルウ』、『ナムコ・ワンダーエッグ』、『パックマンCE 2』、『プラ・ソニック・ラブ!』、『大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U』など多くのサウンドを担当。現在は、作編曲家としてオリジナルCD制作の他、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』、『アリス・ギア・アイギス』など、幅広く活動中。

中西 哲一
1996年、ナムコ(当時)に入社。代表作は「リッジレーサー」シリーズ、「エースコンバット」シリーズ、『サマーレッスン』など。クリエイターとプログラマの橋渡しを得意とし、サウンドディレクター/テクニカルサウンドデザイナーとして多くのタイトル開発に携わる。現在はバンダイナムコスタジオにて所属グループマネジメントやオーディオ技術開発リーダーを担当。

黒畑 喜弘
小さい頃からのナムコ好きが高じ、1998年にナムコ(当時)に入社。『リッジレーサー7』のサウンド実装を機に社内サウンドフレームワーク「NUSound」の開発に携わり、「KORG Gadget」用シンセサイザープラグイン「Kamata」では過去の社内資料を基にC30音源を再構築。代表作は『太鼓の達人』の「スーハー2000」(ボーカル)。
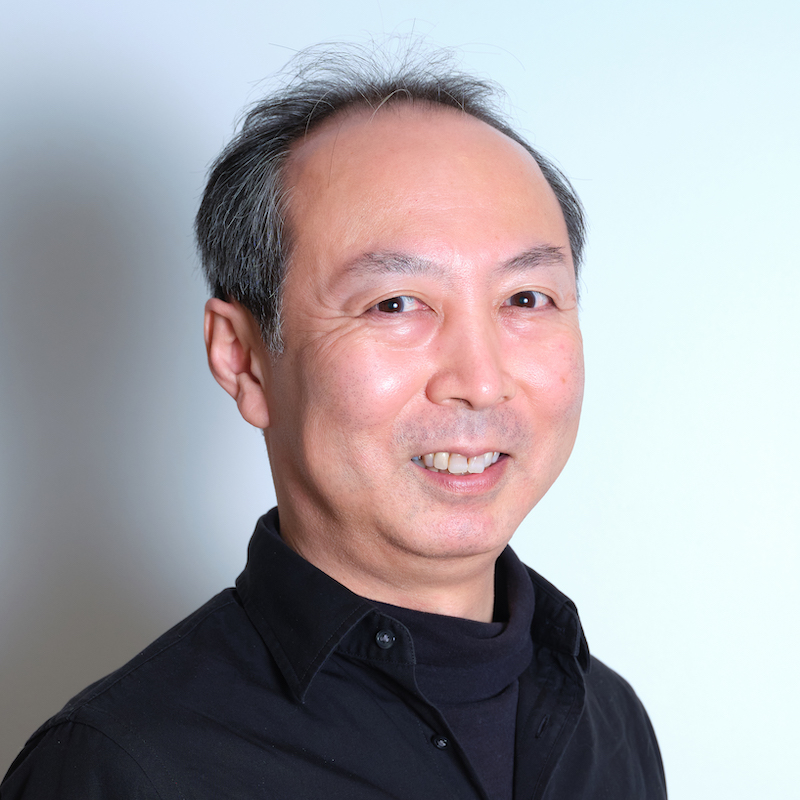
大久保 博
1994年、ナムコ(当時)に入社。代表作は「リッジレーサー」シリーズ、「エースコンバット」シリーズ、「鉄拳」シリーズなど。バンダイナムコスタジオサウンドチームを経て、現在はバンダイナムコ研究所に所属し、XR、AI技術のビジネスプロデュースや新技術「ELMIRAIVE™AX(旧称:BanaDIVE™AX)」の開発等に携わる。
ハードウェア音源からソフトウェア音源に移行したPlayStation3世代

――それでは、試行錯誤が続いたPlayStation2世代から、いよいよPlayStation3世代のサウンド制作についてお伺いしていきたいと思います。
黒畑:PlayStation3世代から、それまであった音源専用ハードウェアやチップが搭載されなくなったんですよ。
中西:そうそう、ハードウェア音源(※1)が消えたんです。
※1 ハードウェア音源:PlayStation2ではSPU2(PlayStationに搭載されたPCM音源(24ch)の発展形で48ch)が搭載されていた。
黒畑:要は全部ソフトウェア、CPUでやらなくてはいけないというか。ハードウェアメーカーさんがサウンドの基本的な仕組みは用意してくださるんですけれども、凝ったことをやりたかったら自分でCPUを叩いて(直接制御して)イチから音を作れる時代がPlayStation3のころからはじまりました。
そこから新たなゲームサウンド表現への技術探求がまたはじまるわけですね。
中西:ドライバをゼロから作ってしまおうということで黒畑くんと一緒にやることにしました。
黒畑:そこでサンプリングした音の音量を変えたりした時に、小川さんがC352(※2)の開発でおっしゃっていた「プチプチ」というノイズが発生する事態にこちらも遭遇したわけです(笑)。「スロープ(※3)をつけないとやはりプチプチ鳴るんだ」って。
※2 C352:PCM32chに対応したナムコカスタム音源。システム基板としてはシステム22などに使われ『リッジレーサー』(1993年)、『リッジレーサー2』(1994年)、『エースドライバー』(1994年)、『サイバーコマンド』(1995年)、『レイヴレーサー』(1995年)などに採用された。
※3 スロープ:音量を一度に大きく変えるとプチプチというノイズが発生するため、スロープ状に徐々に変更すること。
中西:「オーディオ信号制御ひとつもハード時代と同様に簡単じゃないよな……」という現実問題にぶちあたりました。
小川:PlayStation3の時代になって「やった! これでいろいろできる!」と思った?
中西:はい。なんでもできると思いましたね。
黒畑:しかもCell(※4)は当時のCPUとしてはかなり速くて、でもマルチコアすべてを使いこなすのはまだ難しいということで、「だったらサウンドでCPUコアを丸ごと1つ使っていいよ」と言ってもらえたので、それで「ソフトウェアミキシングができる!」と手を付けはじめた感じでした。
※4 Cell:Cell Broadband Engine。異なる得意分野を持つアーキテクチャのプロセッサを1つのCPUに集約した異種混合型マルチプロセッサ。
中西:『リッジレーサー7』がローンチ(本体同時発売:2006年11月11日)タイトルでしたので、本体同時発売で独自ドライバを使用して仕上げるというかなり難易度の高い挑戦をしました。
黒畑:PlayStation3にXbox 360の『リッジレーサー6』(2005年11月22日[北米/カナダでの発売日]日本では同年12月10日)の環境をそのまま持っていこうとしたら、うまくいかなかったんですよ。
だったら、私たちが使いやすいドライバをイチから作ってしまおう、というのをPlayStation3のローンチタイトルでやろうということになったんですね。さんざん痛い目には遭うんですけれど(笑)。
中西:予想以上に大変でした。
黒畑:今考えると、かなり果敢な挑戦で、よくやりましたよね?
中西:うん、今ならこの挑戦は止めるかもしれない(笑)。
黒畑:本当にそんな感じで。だいたい中西さんにそそのかされて……(一同笑)。「音のミキシングって足し算と掛け算だけでいいんだよ」という感じのことを言われて「あ、それでできるんだ!」って。
中西:そそのかしましたねー。でもだいたい合っているよね?
黒畑:合っていますけど……(一同笑)。
ソフトウェア音源化で再びリアルタイムサウンドの生成に挑戦
中西:オーディオ信号処理をやるというのは奥が深かったね。
黒畑:深かったですね。やりたかったことができるようになるまで、想像していた以上に時間がかかってしまいましたが、PlayStation3を使って「ソフトウェアで」作るということができたので、ハードウェアに依存しない、より新しい表現をするための基礎ができたのは良かったです。
中西:それまではサンプラー音源を再生するということがベースにあったんですけれども、『リッジレーサー7』で実験的にやったのが、ソフトウェアでのオーディオ信号そのものをジェネレートする……言い換えるとシンセサイズして音を出そうということをやってみたんです。
サンプリング波形をそのまま鳴らすだけではないエンジン音に挑戦してみました。
黒畑:それまではエンジン音をサンプリングした一部をループさせて、そのピッチを上げ下げして使っていたんですけれども、そのままピッチを変えるだけだとおかしく聞こえたりするんですね。いっそのことエンジン音に関してはイチから生成して作ろうと。
中西:まったく新しい鳴らし方というチャレンジをローンチタイトルでやろうというのはかなり果敢なことでした。
黒畑:その担当は私の同期だったんですが、当時開発部署が入っていた中目黒のビルの中で、彼がヘッドフォンを外してスピーカーで開発チームのみんなに聞かせたら「おおー!」ってざわめきが起こりましたね。
中西:「えっ、そんな音が出るの!?」って。
黒畑:それまでのサンプリング音のピッチ変更とは全然クオリティが違っていて。それができるようになったことがPlayStation3以降の話としては大きかったです。
大久保:毎回、「リッジレーサー」シリーズのローンチは無茶しているけど、『リッジレーサー7』は本当に無茶していたね。
中西:いろんな思い出が蘇りますね。でも信号処理がソフトウェアで実現したことで、やろうと思えばいろんなことが叶えられるという土台ができました。
その後に登場したプラットフォームは、PCも含めてなんでもできるようになって、今でもいろいろ新しい音作りを追求できるように研究が続いています。
小川:ひとつ設計して実現するとそれが後に生きるよね。
中西:そうですね。
黒畑:それが後に生きますよね。

「文字に書けることをどれだけ並べられるか」で実績をアピールすることも大切
大久保:でも全体的に「(自分たちが)やりたくてやった」って動機が大きいよね(一同笑)。
中西:そうですね。やりたくてやっていたんですよね。
黒畑:別にやらなくてもよかったことではあります(笑)。
大久保:あそこまでドキドキする目に遭わなくてもよかったのでは(笑)。
中西:ほんと怖い目に遭わなくてもよかったです。
大久保:ここまでがんばっても、雑誌やウェブなどのテキストメディアだとサウンドのすごさってなかなか伝えられないんですよ。いろいろおもしろいことを仕込んでも、「音は記事にしづらいんですよね……」と言われてしまうんです。そういう対応が多かったですね。
ですので、それを聞いて『リッジレーサー7』でサウンドディレクターとして「とにかく文章でも『なんかすごい』が伝わる話題をどれだけ並べられるか」というのを目標にして無茶を増やしていたところはありますね。
フルサラウンド対応、エンジンサウンドのシンセサイズ、インタラクティブミュージックなど、PlayStation3の最初のタイトルだから、これまでのゲーム機ではできなかった部分は、できるだけ記事にしてほしいなという思いも込めてやっていた記憶がありますね。
中西:ああ、やりましたね。サラウンド対応(※5)。
※5 サラウンド対応:『リッジレーサー7』は効果音とBGMも全てDolby Digital 5.1chサラウンドに対応した。
大久保:そういう「言葉にした時に、ある程度引っかかることを並べられるようにしないと、話題にもならないや」と思って。
サウンド担当としては良い音を作って鳴らしてユーザーの皆さんに喜んでもらうということだけではなくて、皆さんに届けた時にどれだけ良いもの、すごいものを手に入れられたか、満足度というか買うだけの価値があったと思ってもらえることを意識しなければならないということを考えています。
そのために「言葉にできる=人にも自慢できる」ということを意識して形にして、メディアの皆さんに話していったら、オーディオ雑誌の方やオーディオメーカーさんからも声がかかりはじめて。それが記事になりはじめるとやっと「おお、なんかサウンドすごいね」と認めてくれたのがすごく心に残っていますね。余談ですけど(笑)。
中西:ローンチタイトルとしての「リッジレーサー」シリーズの開発というものは、「自分たちが新しいベンチマークを作る」という意義があったと思っています。
「ここまで(クオリティレベルを)上げるからね」、「この後みんな大変になってしまうよ」となるようなことをわざとやってやろうと思っていたので、ある意味「挑戦状」でしたね。
だから正直かなりの無理をしたのですね(笑)。「ここまでがんばったら他社さんもこれに続いて、これを超えていかなくてはいけない」という状況にしたいと思っていました。
黒畑:当時どのハードでもまず「リッジレーサー」シリーズがクオリティの基準のひとつになっていましたからね。
フォーマットを共通化することで過去のデータも引用できる環境に

――少し話を戻すようですが、「NUSound」は『リッジレーサー7』では何世代目になっていたのでしょうか?
中西:「NUSound」の名称自体はその前から開発がはじまっていて、『リッジレーサー7』の時は「NUSound2」の移植に挑戦していたころですね。もうデータをExcelで作るところは継承されていて。
データをExcelで作るようにしたことはサウンドクリエイターとしてもとても良かったことだと思っていて、今でもツールやアプリがなくても当時のデータが見られるんですよ。それにはとても助けられていますね。
黒畑:Excelは高機能なツールなので、やはり便利になりました。独自のツールを作らなくてもいいし。
中西:ツールを作らなくても済むというのはよかったね。
黒畑:Excelのスキルが上がるとどんどん使いやすくなっていくという(笑)。
中西:そのあと「NUSOUND3.0」以降は編集ツールも作っていますがやはりツール作りは大変でしたね。仕様的なものは「NUSound2」で作ったものがだいたい継承されている感じです。いろんな可能性が広がる土台がそのころに構築されてきたんですね。
――お話を伺っていると、制作過程においてほかの要素が出来上がってから本格的な作業がはじまったり、使用メモリやスペックに制約があったり、制作期間にしわ寄せが来きがちだったサウンド関連の開発においても、NUSoundは貢献したのではないかと感じました。
ナムコサウンドの志を受け継ぎ、常になんとか先に進めたい
――第2章はFM音源の採用から独自のPCM音源の実現、そして家庭用においてはCDメディアの導入からソフトウェアによる信号制御、サラウンドの実現など、環境が激変してきた幅広い時代のお話を伺ってきました。皆さまのお話からは、ナムコ(当時)から「インタラクティブ性」など、ゲーム体験に伴うサウンドの制御をプログラマーとともに叶えていくということをとても大切にしてきたことが、結果仕事やそれに連なるサウンドプログラマーやクリエイターの方々の思いとして、第1章のレジェンドクリエイターの方々から受け継がれてきたのだと感じられましたが、実際のところはいかがですか?
大久保:そうですね。あとはね、常に「負けたくない」と思っていたんですよ。ブランドとして「こういうのがナムコサウンドだぞ!」と言っていたくて。皆さん、そういうのなんとなく思っていませんでした? (と全員に向く)僕はずっとそう思っていたかった。
中西:ほかと違う挑戦をし続けていないと、それが示せないので、毎回何かやろうとしていますよね。
大久保:これまでの時代を進められてきた大先輩の方々がいて、常に先端でしたし、それを進めていたナムコ(当時)という会社に入って、なんというか「ゲームサウンドってこうだよね? という固定観念に流されていくようなサウンドチームになってはいけないな」という思いがあって。ナムコサウンドのブランドとして受け継いできたものを消したくないという思いと、先輩たちを見習って、常になんとか先に一歩進めたい、という話を中西さんとしていましたね。
――中西さんは今バンダイナムコスタジオでどんなことに取り組まれていますか?
中西:現在もサウンド技術開発をリードするオーディオテクニカルディレクターのような役割をしています。オーディオ表現がソフトウェアベースになってからはやれることにキリがありません。テクノロジーは進化していくので、新しい「やりたいこと」が常に足されていきます。飽きることはありませんよね。いまだとAI技術をいかに開発で活用していくかなどが注目トピックになってきます。
またサウンド分野に限らない組織運営や開発全体の課題解決にも取り組んでいます。ここまで技術の話ばかりしてきましたが、マネジメント業務もキリがありません。テクノロジーを使う「人」たちの心情と行動の変化もおもしろいんです。マネジメントでチーム全体のモチベーションも変わりますし、提供するツールのUX設計ひとつで心情に変化が生まれ生産性に影響します。人と技術がきれいに繋がり、開発に携わるクリエイターたちの創造や生産性を高めていくことにやりがいを感じています。
――黒畑さんは今どんなことに取り組まれていますか?
黒畑:当時はこの先ずっと使えるライブラリ(NUSOUND3.0)を作ったつもりで、実際、いろんなタイトルで使ってもらってきたんですが、やはり10年も経つと考え方が古いところが見えてきたので、未来は情熱ある若者たちに託すことにしました。
今は久しぶりにゲーム開発の現場に戻っていて、改めて使う側に立ってみると、至らない点がいろいろあったのがわかって反省しきりです。他社のミドルウェアも使ってみたりして、今までとは違った視点でフィードバックしています。
あと、たまに歌を歌ったりもしています(笑)。(4曲目の「Switchback」)
――大久保さんは今バンダイナムコ研究所でどんなことに取り組まれていますか?
大久保:バンダイナムコ研究所は、AI技術などグループの先端R&Dを担う会社で、その中で私はAI音声技術やAI対話技術などをさまざまな形で活用して、エンタメや社会にアウトプットしていくためのプロデュースを担当しています。同時にクリエイターとしても『鉄拳8』(2024年1月26日)や、『電音部』などゲームやIP(※6)コンテンツへの楽曲参加、外部企業のクリエイティブのディレクションなども担当してます。いつまでもクリエイターでありたいし、常に未来を見ていたいんですよね(笑)。ナムコってそういうブランドでしたよね。なので、いまだにやりたいこと、知りたいことをずっと追いかけている感じですね(笑)。
※6 IP:Intellectual Property=キャラクターなどの知的財産
――逆に、バンダイナムコグループを卒業された細江さん、川田さん、小川さんには、今でも現役としてサウンドに携わってきている皆さんから見て、今のバンダイナムコはどう映ってきたのかをお聞きしたいのですが?
細江:外に出て、大きな会社を見てみると、小さな会社では難しいことをできるからいいな、とは思いますけれど。近頃は、どんどんいろんな便利な道具が出てきて、差は縮まってきたな、と思います。ミドルウェアなど環境がよくなってきて、わりと近くなってきたかなと。それでもうらやましい感じはしますね。
黒畑:確かにミドルウェアが充実してきましたので、逆にこちらのプレッシャーもすごいですね。
中西:それでできないことって何だろう? ということは考えています。ミドルウェアに乗っかって、そのうえで差別化を図るというアプローチもありますよね。例えばプラグインを独自に開発するということを私たちもやっていますので、他社さんにないものを作り上げるということはミドルウェアを使ったとしてもやり続けていますね。
川田:今はサウンド制作だけに限らないですけれども、物量的にもクオリティ的にも本当に高いところを攻めないと商品として差別化できないという。
黒畑:物量は本当に恐ろしいぐらいですね。
中西:大変なことになっていますね。
川田:その中でテクノロジーを伸ばしていくのは本当に大変なことなんだろうなと。それでもやはり「次は何をやってくれるのかな?」という期待があって、これから先、どこへいくのか楽しみだな、という風に外からは見ています。ぜひ何かやってほしいとは思っていますね。
中西:まだ可能性はたくさんあると思っています。例えばDAW(※7)でできることがゲームでまだ全然できていないじゃないですか? それが少しずつでも(ゲームに)入ってきて、「あ、これができるようになったんだ」ということが増えていくのではないかと期待しています。
※7 DAW:Digital Audio Workstationの略。録音、編集、ミキシングなどが行える楽曲制作ソフトウェアのこと。
黒畑:「『ProTools』と同じことができるくらいのものを作って」と言われてまだできていないですからね。
中西:それに、かつての音源でできていたことがいまだにできないこともまだありますね。昔のエミュレーターのようなものはランタイムに乗るようになってきたので、同様の表現ができるチャンスはあるかもしれませんね。それをさらに発展させることもできるかもしれないので、挑戦を続けていく、という感じでこれからもやっていきます。
川田:楽しみですね。
大久保:前回含めて、これまでの話を聞いてきて、ナムコサウンドには、これまでゲームサウンドがゲームのサウンドとしてどういう表現や体験設計ができるか? という今のゲームサウンドの基本ともいえるような部分を、早く素敵にやってきている歴史があって。今あるサウンドのミドルウェアに入っている機能も、昔皆さんが考えて作ってきた要素が今の技術に置き換わってはいますが、本質のところは変わらず、当時基礎の部分を先輩方が作ってこられて今のスタイルに発展してきているんだなというのをすごく感じます。
そういう技術アプローチができるサウンドクリエイターとサウンドに愛のあるプログラマーが一緒になって実現されていくスタイルがナムコ(当時)らしいなと感じたことなんですよね。細江さんの「リッジレーサー」シリーズのBGMもデータみたらほぼプログラムだったり(笑)。
川田:『妖怪道中記』のデータを見てもらったときに「ほとんどプログラムだね」と言われて。かなり音色を書き換えていて、しかもコマンドだらけ。自分で見てもよくわからないところがあったりして(一同笑)。
細江:『妖怪道中記』のソースを見るとたまにしか音符がない(一同笑)。
大久保:それはちょっと見直したいですね(笑)。
中西:サウンドクリエイターの皆さんがどんどん遊べる要素を足していって、かつて遊んでいたようにいくらでも凝ったデータができるということをまた取り戻したいですね。
大久保:やりたい気持ちを叶えられる自由度みたいなところはまだ発展の余地があるんでしょうね。
――最後に小川さんからも一言お願いできますか。
小川:サウンドは「上から評価されない」という話が出ていましたが、人によって重視する人もいれば「鳴っていれば(良しあしが)わからない」などいろんな人がいるので、音楽に精通している周囲メンバーと組めなかったサウンド担当者はフラストレーションを感じるのではないですか?今回歴代のサウンド担当者が集まって話をする機会ができたのはそういう面でも大事だなと思いました。
あとやはり「遊び心」ではないですけれども、ゲームの企画書からそれをどう表現するのかというのはプログラマーさんやサウンドの担当者の思いが入ってゲームという製品ができていた時代だったと思うんですよね。それぞれの思いが結集して初めていいものができていったのだなと思います。
今は制作する物量も多いなど、今のゲーム制作現場の皆さんは大変だと思います。昔はそこまで規模も大きくなくて数人で作ることができて、それぞれ「遅れましたすみません」で済まされる時代だったので、当事者も「いい時代だったな」というと思うんですけれど、そういうゆとりが今はないのではないかな、と想像します。
中西:今はその余裕を作り出すためにみんな工夫を続けていますし、隙あらば何かやりますよね(一同笑)。ありがとうございました。
――長時間にわたる貴重なお話の数々、ありがとうございました。

「電音部」について詳しくはこちら
「Bandai Namco Game Music」についてはこちら
※バンダイナムコ知新では、当時の資料や関係者への取材をはじめ、皆さまの知見もお借りし、できる限り正確な記事を目指しております。事実と異なる場合がございましたら、後日訂正をさせていただきますので、予めご了承いただけますと幸いです。
【※本記事に引用している参考資料につきまして】
・本文中のBGMや効果音などの音源へのリンクは、お客さまのご利用環境によってアクセスできない場合があります。
・動画は、移植版タイトルのものを引用しています。
【補足】タイトル後の年号はアーケード版は稼働開始年、家庭用版は発売日を表記しております。
【編集後記】
ハードウェア音源が消え、ソフトウェアによる音源制御となったPlayStation3以降の家庭用ゲーム機向けのサウンドシステムで、内製のサウンドシステムを新たに作ることで、DAWでは簡単にはできない「ゲームに特化したインタラクティブな表現」を追求していくことが、ナムコサウンドの精神の継承にもつながっていたことは非常に興味深いものがありました。
第8回第2章も大久保さんにアドバイザー兼インタビュアーとしてご協力いただきました。また、インタビュイーの皆さまにも内容をご確認いただき、当時の貴重な情報を追加していただきました。
長きにわたった第8回も、これにてしめくくりとさせていただきます。ありがとうございました。
取材・文/佐伯 憲司
ライター/編集者。ゲーム関連本、ニュースサイト、攻略映像などに関わったのち、現在フリー。プロモーションビデオなどでサウンドに惹かれてゲームに触れることも増え、ゲームにおけるサウンドの発展を肌身に感じてきた世代として、今回の企画を通じてその影響の大きさとクリエイターの方々の思いをお伺いできました。





1979年、ナムコ(当時)に入社、半年の営業研修後、ビデオゲーム開発部署に配属(当時『パックマン』を試作中)。『ギャラガ』プログラマーを担当後、ハードウエア開発、3Dハード前までの各種ハード、システム基板、カスタムICなどの設計を担当。JAMMA VIDEO規格専門小委員会に参加(副委員長)、通信プロトコル草案の策定にも携わる。PlayStation®︎互換アーケード基板「SYSTEM11」をSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント:当時)と共同開発。量産治具「フラッシュライタ」を製作。その後、役職定年で希望してAMサービス部に転籍。アーケードハードの修理を現在行っている。